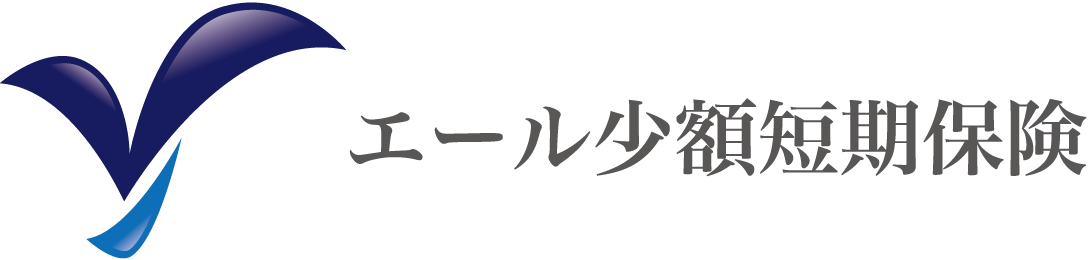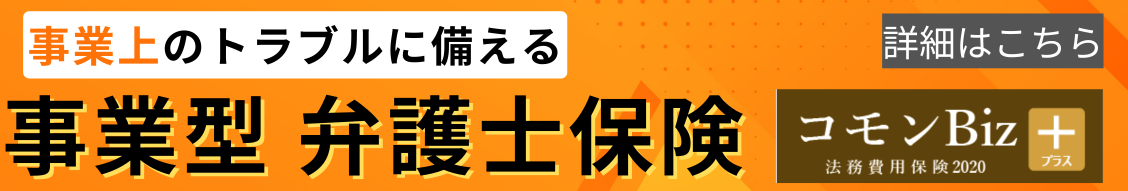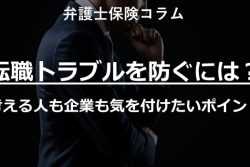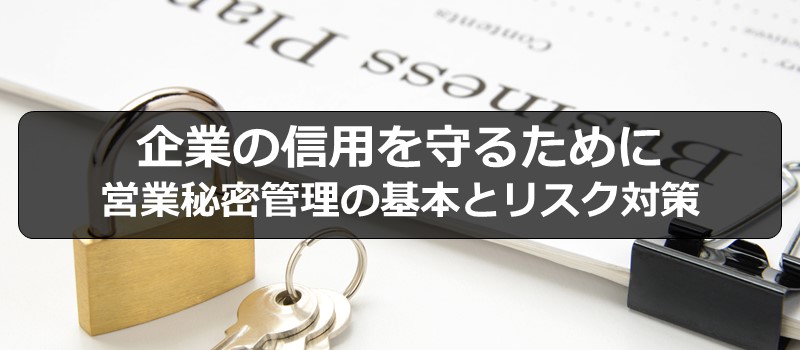
近年、企業や従業員が、営業秘密 (顧客名簿、マニュアル、仕入先リスト、財務データ等の秘密情報) を外部に漏洩し、逮捕・検挙・書類送検されるという事案がたびたび報道されています。
相次ぐ情報漏洩を受け、情報管理の重要性は日々高まっています。
今回は、営業秘密はどのようなものが該当するのか、また漏洩した場合のリスク、事例を通して事業主として講じておくべきこと、従業員として注意すべきことをみていきます。
1 不正競争防止法上の営業秘密とは
営業秘密とは、「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3つの要件を満たした情報を指します。
① 秘密管理性:秘密として管理されていること
例:営業秘密を含む紙媒体などに「confidential」、「秘」の表示をすること
電子データをアクセス制限のされたフォルダに保存すること
② 有用性:事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること
例:実験データ(失敗した実験データも含まれます。)
③ 非公知性:一般的には知られておらず、または簡単に知ることができないこと
例:企業の関係者だけが知っている情報
インターネットや本などで簡単に入手できない情報
上記要件を満たさないと、不正競争防止法上の保護を受けられなくなります。
営業秘密として持ち出されては困る情報について、要件を満たす管理をしているか、事業主の皆さまはこの機会にご確認ください。
2 営業秘密を漏洩した場合のリスク
営業秘密を漏洩した場合、以下のリスクがあります。
① 刑罰を受けるリスク
(1) 不正競争防止法違反
10年以下の懲役*もしくは2,000万円以下の罰金またはその両方(法人は罰金のみ)
*令和7年6月1日以降は「拘禁刑」
(2) 個人情報保護法違反(個人情報が含まれる場合)
1年以下の懲役または50万円以下の罰金(法人は罰金のみ)
② 民事上の損害賠償請求を受けるリスク
③ レピュテーションリスク
④ (漏洩者は)社内規程違反による懲戒処分等になるリスク
3 営業秘密の具体的な漏洩事案
事案①
2020年9月、大手回転ずしチェーン店(企業A)の元幹部(Cさん)が同社の営業秘密である商品原価、食材の種類、仕入れ値などのデータを不正に取得し、同年11月に競合他社(企業B)の社長に就任(転職)。
転職後、企業Aの上記データを企業Bの社内で開示したとして、逮捕されました。
2023年5月、Cさんに対し、懲役3年(執行猶予4年)、罰金200万円の判決がくだりました。
上記事案では、営業秘密を漏洩した人(Cさん)のみならず、営業秘密を受け取った側(企業B)も罰金等の刑事罰の対象となります。
また企業Bは、相手先企業(企業A)から損害賠償請求を受ける場合があります。
企業Bは、不正競争防止法違反で刑事裁判を受けているとともに、民事裁判では企業Aから5億円の損害賠償を求められています。
2023年、大手学習塾(企業D)に勤務していた講師(Eさん)が、塾に通っていた複数の女児を盗撮し、氏名、住所をSNSに投稿。
Eさんは東京都迷惑防止条例違反で逮捕され、企業Dも個人情報保護法違反で書類送検されました。
(営業秘密に個人情報が含まれている場合)営業秘密を漏洩させた人(Eさん)だけでなく、その人が所属している 企業(企業D)も刑事罰や損害賠償請求の対象となる場合があります。
上記事案では、いわば被害者とも言える企業Dも両罰規定(法人に所属する役員や従業員らが、法人の業務に関連して違法な行為をした場合、個人だけでなく、法人も併せて罰せられる規定)により書類送検となりました。
4 事業主として講じておくべきこと
以上の内容を踏まえて、営業秘密の漏洩を防ぐために、企業として講じうる対策にはどのようなものがあるでしょうか。
一例として、以下のようなものが考えられます。
・営業秘密へのアクセス権限者を制限。
・認可外のサイトへのアップロード禁止。
・通信ログの監視。
・個人所有のUSBメモリ等、外部記憶媒体へのファイルコピーの禁止やシステム制御。
・紙媒体の営業秘密は、秘密である旨の明示。また、その他の情報と区別した上で、施錠保管。
・就業規則で営業秘密等の情報漏洩をした場合について取決め。また、誓約書の取り交わし。
・情報の管理・取扱いに関する社内講習の実施。
営業秘密を漏洩させない、持ち込ませないために、事業主としては必要な措置が講じられているか確認し、足りないと思われるようなところがあれば、改めて対策を検討するのが肝要です。
5 従業員として注意すべきこと
従業員の立場であれば、どのような情報が営業秘密に該当するのか、どのようなことをしてはいけないのか、認識しておきましょう。
営業秘密の不正取得や勝手な持ち出し、報酬目当ての横流し、不正入手した情報をもとに製品開発や実験等、してはなりません。
また、広く当てはまる注意すべき事項としては、以下のようなものがあります。
・公共の場で営業秘密に関する話をしない。(飲み会、カフェでのテレワークなど)
・紙媒体の営業秘密の廃棄時、シュレッダー等を利用。
・会社の許可なく、仕事で個人のパソコン、スマートフォンを使用しない。
・異動、退職時の適切なデータ消去。
・勤務先の就業規則など(営業秘密等の情報漏洩をした場合)のルールの理解。
営業秘密の情報漏洩をした場合、前述のとおり、刑事上の責任や民事責任を問われる可能性があります。
自身がトラブルに巻き込まれないためにも日頃から営業秘密の取扱いに関して、心がけておきましょう。