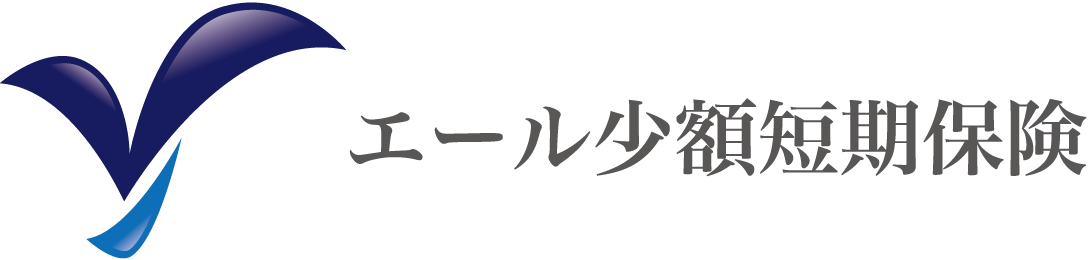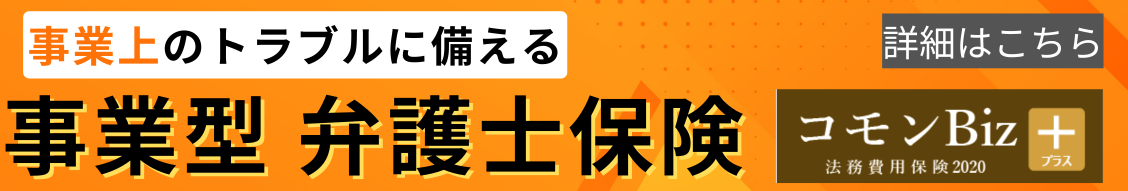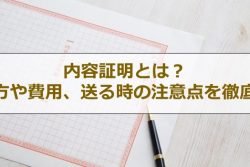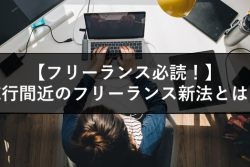新型コロナの影響により一時期は自粛を迫られていたが飲食業界ですが、近時はその活気を取り戻しつつあります。
飲食業界における特徴的なサービスのひとつが「飲み放題」です。
飲み放題サービスの具体的な内容はどのようなものであるのかについて、法的な観点から捉え直してみましょう。
【事例】A氏は、学生時代の友人たち数人とB店の飲み放題を注文しました。
この飲み放題のラストオーダーの際、飲み足りなかったA氏は瓶入りの日本酒1本を注文しました。
A氏は飲み放題中には盃1杯分だけ飲み、退店時にお酒の残っている瓶を持ち帰ろうとしました。
店側は拒みましたが、A氏は「飲み放題で注文したのだから、この酒は俺のものだ。」などと主張しています。
この事例において、A氏が日本酒を持ち帰ることができるかどうかは飲み放題というサービスがどのような利用方法を想定しているのか、法的にいえば飲食店とA氏との間の酒類提供契約をどのように解釈すべきかにより決まります。
この契約を解釈するに当たっては、酒類販売業を巡る法規制を理解することが有益です。
酒類の販売には免許を要するのが原則ですが、店内で飲ませるために酒類を提供する飲食店については、酒類の販売業免許は不要とされています(酒税法9条1項ただし書)。
しかしながら、国税庁の通達によれば、「営業場以外の場所で飲用に供されることを予知して、酒類をその営業場で消費者に継続して販売……する場合」には、原則どおり酒類の販売業免許が必要となります。
このような酒税法の解釈を踏まえると、飲食店とA氏との間の酒類提供契約の内容をクリアに理解することができます。
すなわち、酒類の販売業免許を有する飲食店はあまり多くないと考えられますから、基本的には店内での飲酒が前提とされていると考えられます。
そうすると、飲み放題サービスにおいては、飲み残しを持ち帰ることはできないと解釈するのが合理的です。
これに対し、A氏は独自の理解をもとに日本酒を持ち帰ろうとしているわけですが、これは法的な根拠のない不当要求(いわゆるカスタマーハラスメント)に該当します。
店側としてはこのような不当要求に毅然と対応すべきですし、客側としてはお酒が入って気が大きくなったとしても不当要求をしないよう日頃から気を付けるべきでしょう。